改めまして!事業ログ編集長のノグチです。
この記事では個人事業主の定義やデメリット・メリットなどを紹介しています。
個人事業主の定義を詳しく知りたい人はこの記事を、今すぐ行動したい人は公式サイトを確認しましょう。
個人事業主の4つの定義を紹介!それぞれの特徴や注意点は?
ここでは個人事業主の定義についてまとめています。
主に4つの定義があるので、特徴や注意点を確認しておきましょう。
定義①:自ら独立した事業を行う自然人
個人事業主(こじんじぎょうぬし)は自ら独立した事業を行う自然人を指す。
日本の法律では消費税法基本通達1-1-1において自己の計算において独立し、事業を行う者、同第2条1項3号では事業を行う個人と定義され、慣習的には個人事業者(こじんじぎょうしゃ)または自営業者(じえいぎょうしゃ)とも称される。
株式会社等の法人事業を設立せず、サラリーマンのように雇用される者としてでもなく、独立した事業として継続的な下請(業務契約)や納入、代理店などの雇用ではない契約(請負や委任等)で他者の事業に従属する。
事業主一人、家族、あるいは少数従業員の小規模経営が一般的だが、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではない。
定義②:「開業届」を税務署に提出し受理されていること
個人事業主になるために、必要な資格や経験はありません。
「開業届」を税務署に提出し、受理されれば誰でも個人事業主になれます。
なお、提出先となるのは原則として納税地の税務署です。
定義③:独立・反復・継続し一定規模の仕事をしていること
個人事業主とは、法人設立ではなく、個人として事業を経営する事業者のことです。
事業であるかどうかは、確たる基準があるわけではありませんが、次のような点について総合的に判断します。
継続的、反復的な経済活動であるか
営利性(利益を得ることを目的としている)を伴うか
独立性(自己の判断と責任で活動している)があるか
対価性(サービスや商品に対して相当の対価を受けている)があるか
独立・反復・継続して一定規模の仕事をしている場合は、その仕事は事業となり、個人事業主として仕事をしていることになります。
会社員の副業であっても、これらの判断により事業かどうかが問われます。
定義④:新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
個人事業主の所得は「事業所得」や「不動産所得」等となり、会社員の副業の多くは「雑所得」に区分されます。
個人事業主のデメリット
個人事業主は、デメリットや注意すべき点があります。
自身が個人事業主に向いているかどうかを確認するためにも、デメリットを確認しておきましょう。
社会的な信用度が低い
法人を設立するよりも個人事業主として開業する方が簡単なため、個人事業主は社会的な信用が低くなりがちです。
会社の中には、個人との契約を避けて法人との取引を希望するところもあります。
個人事業主だとビジネスチャンスを逃してしまう可能性があるため、機会損失につながる恐れがあります。
収入が不安定になりやすい
個人事業主の収入は、自分の売上によって決まります。会社員や公務員のように、毎月決まった日に、安定的に給与を受け取れるわけではありません。
つまり、個人事業主は収入が伸びやすい反面、不安定にもなりやすいです。
今月の売上が好調でも、来月以降も好調が持続するとは限りません。
事業運営では様々な経費が発生するため、収入が不安定である点を織り込んだうえで、資金繰りを考えましょう。
事業で収入を得られないと、生活にも支障が出てしまう可能性が考えられます。
個人事業主として独立する場合は、十分に貯蓄をしてからでないと、精神的にストレスを抱えるかもしれません。
融資を受けにくい
個人事業主は、法人に比べて金融機関からの融資を受けにくいというデメリットがあります。
融資の過程では信用度が評価項目の一つとなり、信用を得づらい個人事業主は「貸し倒れのリスクが高い」と評価されやすいのです。
また、個人事業主は事業資金と個人の生活費が混在しがちで、金融機関からすると正確に財務状況を把握できません。
審査に通過できたとしても、融資額が少額になるケースも考えられるでしょう。
利益が多いと税負担が重くなる
個人事業主に適用される所得税と、法人に対して適用される法人税では税率が異なります。
所得税の最大税率は45%で、課税所得が増えてくると税負担が法人よりも重くなる可能性があります。
個人事業が軌道に乗ったら、法人化を検討すると良いかもしれません。
一般的に、課税所得が800万円~900万円程度になると、法人化をしたほうが税負担を抑えられるといわれています。
個人事業主のメリット
昨今は副業を容認する企業が増え、さらに働き方が多様化している関係もあり、「個人事業主として働きたい」という考えを持っている方もいるのではないでしょうか。
個人事業主は自由な働き方を実現しつつ、収入を伸ばせるメリットがあります。
以下で、メリットを詳しく解説します。
自由な働き方を実現できる
個人事業主は自分が事業主となるため、働き方に関する自由度が高いというメリットがあります。
勤務する曜日や時間に関する決まりはなく、働くタイミングを自由に決められます。
土日祝日にとらわれず、自分のスケジュールで休日を設定できる柔軟性の高さは、個人事業主のメリットです。
時間だけでなく、働く場所も自由です。
自宅で働く・オフィスを構える・コワーキングスペースやカフェで作業する等、その日の気分や都合に合わせて、仕事場所を自由に選択できます。
このように、仕事の裁量はすべて自分次第となるため、自分にとって最適な就労環境を自分で用意できます。
収入が伸びやすい
個人事業主は、事業が成功すれば会社員よりも収入が伸びやすいというメリットがあります。
スキルや実力、生み出した付加価値に応じた報酬を得られるためです。
こなした仕事量や提供した付加価値次第では、会社員時代よりも高収入を得られる可能性があり得るでしょう。
一般的に、会社員や公務員は年に1回~2回の昇給や昇任しか、収入アップの機会がありません。
一方で、個人事業主は自分の努力や工夫次第で収入を伸ばせるため、「収入が増える→さらにモチベーションがアップする」という好循環を生み出せます。
税務申告が比較的簡単
個人事業主には年末調整という概念がないため、自分で確定申告を行わなければなりません(税理士に依頼することも可能)。
しかし、個人事業主の税務申告は法人よりも手続きの負担が軽く、過重なリソースを割かずに済みます。
個人事業主が青色申告特別控除で55万円または65万円の控除を受けるためには、やや複雑な「複式簿記」で記帳する必要があります。
しかし、会計ソフトを活用すればそこまで手間がかからないため、簿記の知識がない方でも税務申告を行えるでしょう。
経理の事務負担が軽い
個人事業主は日ごろから事業の帳簿を付ける必要がありますが、経理の事務負担は法人よりも軽いというメリットがあります。
また、給与・税金・社会保険関係の処理も比較的簡単です。
個人事業主は、報酬の受け取りや社会保険の手続き、保険料の納付が比較的シンプルです。
事務負担が軽ければ、自分の事業に多くのリソースを割けるメリットが期待できるでしょう。
こちらから詳細を確認してご自身にあったツールをチェックしてみてはいかがでしょうか?
>>弥生のかんたん開業届の詳細はこちら
個人事業主になれない人は?副業禁止の人
本業の規則等の関係で、副業として個人事業を始めることができない、または認められない場合もあるため、本業の規則を確認しておきましょう。
副業が禁止されている企業に勤務している場合、副業として個人事業を始めてしまうと罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
ただし、企業の就業規則は法律ではないため、抵触しても法的な罰則は受けません。
公務員の副業は、国家公務員法や地方公務員法で制限されています。
抵触すると法律に基づく命令に違反したことになり、懲戒処分を受ける可能性があります。
そのため、基本的に公務員の身分を有しながら個人事業主になるのは現実的とはいえません。
個人事業主になるには?開業届けに必要な手続き
個人事業主になるには税務署に開業届を提出する必要がありますが、開業届に必要事項を記入したり、併せて提出する書類を準備したりするには、意外と時間や手間がかかります。
個人事業主の開業手続きを手軽に行いたい場合は「弥生のかんたん開業届」がおすすめです。
「弥生のかんたん開業届」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、個人事業主の開業時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。
パソコンでもスマホでも利用でき、開業届をはじめ、青色申告承認申請書など開業時に提出が必要な書類をスムーズに作成することができます。
また、開業後は、日々の帳簿付けや毎年の確定申告が必要になります。
個人事業主についてまとめ
個人事業主は、法人を設立せずに独立して事業を行う自然人のことです。
開業届を税務署に提出することで、誰でもなることができます。
会社員と比べて社会的な信用が低く収入が不安定になる可能性がある一方、働き方の自由度が高く、事業が成功すれば収入を大きく伸ばせるメリットがあります。
また、税務申告や経理の事務負担が法人よりも比較的少ないのも特徴です。
公務員や勤務先の規定で副業が禁止されている場合は、個人事業主になるのは難しいので注意が必要です。
最新情報をチェックしたいなら、以下の公式サイトを確認して下さいね。
>>弥生のかんたん開業届の詳細はこちら

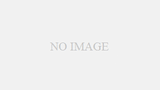
コメント